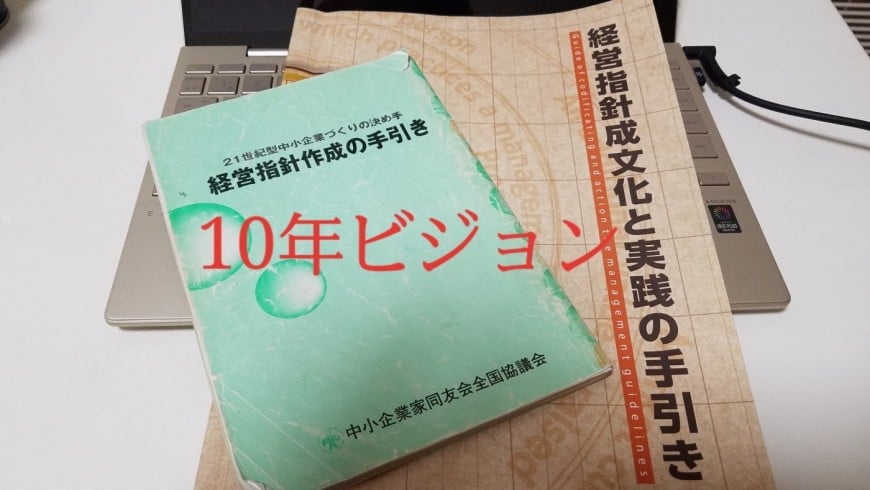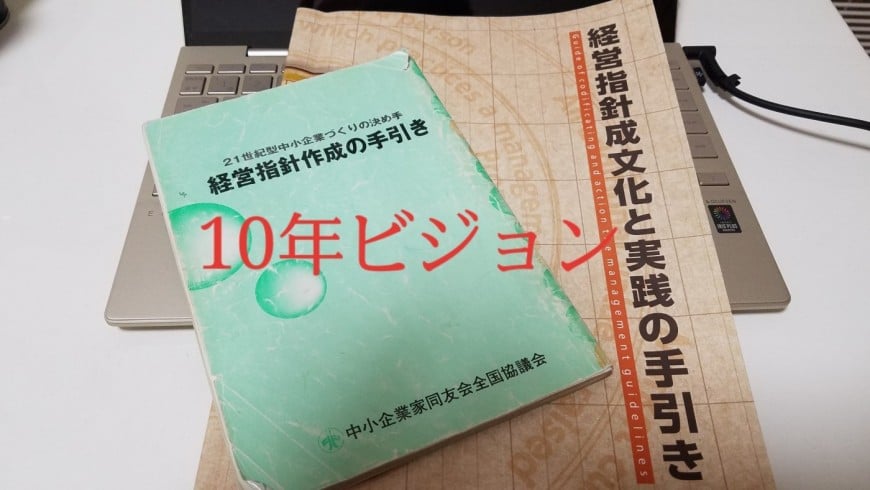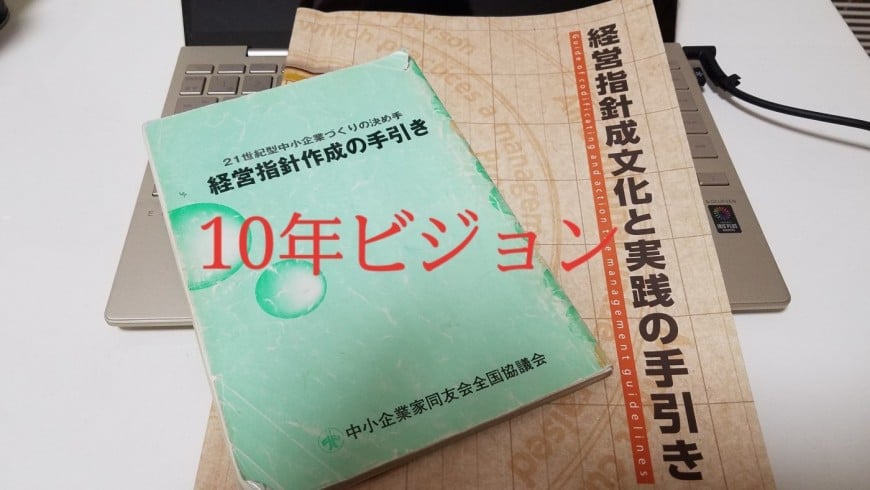後継社長の成長ブログ
渡辺農機のブログへようこそ!
こちらでは、社長業を通じて日々の出来事や学びを「どう成長につなげられるか」をブログとして紹介しております。
ブログ
経営指針の学び24
2021-04-23
日常の学び
経営指針成文化と実践の手引き、10年ビジョン策定にあたってを読んで。
10年ビジョン検討シートは、
1、こんな会社にしてみたい、こんな仕事をしていたい
2、こんな経営者になりたい
3、社員と働く姿やこんな社風をつくりたい
4、取引先や地域や社会とこんな関係でありたい
以上の4項目の検討から作り上げていきます。
本日は、「こんな会社にしてみたい、こんな仕事をしていたい」について
10年後の市場にどのような商品・サービスを提供していきたいのかを考えるにあたって、現在の市場の変化、事業定義、主要商品、売上金額、利益額、資本金などをどうしていくかを検討することが必要です。といったことが書かれています。
社内のことについては3番目の検討事項ですので、ここでは外向きのことについて考える項目なのでしょう。
では10年後の市場については、大きく分ければ拡大していくのか、現状維持なのか、衰退していくのかの3種類です。その中でどのようにしていくかを考えるといいかもしれません。
拡大するから良いとか衰退するから悪いといった考え方は危険です。先日も先輩経営者とお話しましたが、むしろ衰退産業の方がやりやすいという部分では共通認識でした。小さな企業であるほどその傾向は強く感じます。変化する力やスピードが重要だからです。
永続的に繁栄させていくために何をすべきか、そして何をしたいのか、すでに頭にあり形作られてきています。その考えをシートに埋めていきます!
経営指針の学び23
2021-04-22
日常の学び
経営指針成文化と実践の手引き、10年ビジョン策定にあたってを読んで。
策定の前段の最後は、自分や社員の10年後の年齢構成、持つべきスキルや能力、組織規模や集団のあり方や価値観、生き方、働き方がどうなっているか。
これらを考えると10年後が近く感じたりします。
年齢などの定量情報は表やグラフ、数値化しにくい定性情報は言語論理手段だけでなく絵や図などにビジュアル化すると伝わりやすくなるということが書かれています。
やっぱり年齢構成を考えるとリアリティが出ますし、「どんな価値を提供したい」が見えていれば「どんな状態にしたい」が見えてきます。どのように生き、どのように働くのかは「どんな価値を提供したいのか」と行ったり来たりしながら考える内容なのかもしれません。
提供したい価値にあった生き方、働き方になっているのか?または理想の生き方、働き方をしながら提供できる価値なのか?
しっくりくるまで考えてみなきゃです!
こうした構成要素を明確にするために「10年ビジョン検討シート」がありますので「10年後のありたい姿」を描くために活用しましょう!
シートの内容については明日以降のブログで紹介します。
新たな価値
2021-04-21
日常の学び
経営指針成文化と実践の手引き第、10年ビジョン策定にあたってを読んで。
【新たな価値の創造】
10年後に自社は
どのような新しい価値を
どのように想像し
どれくらいの質量で提供しているのか。
と手引きに書かれています。
この質問に対してイメージしようとすると難しく感じます。今これから取り組もうとしていることがどうなっているかを考えるくらいしかできません。
ですので、最後の「提供しているのか」の部分を「提供したいのか」に変えて考えた方がいいように思います。
どんな価値をどうやって想像しどれくらい提供したいのかです。
夢や希望を描くということです。この考え方も難しいと感じる人もいると思いますが、どっちにしても計画や実行に近づいていくと自然と現実に引き戻されます。だったら今時点では好き勝手に自分の理想を妄想したらいいんじゃないかなって思います。
苦しみながらやるセッションではなく楽しみながらやるセッションということで(^^
入り口のハードルを下げる
2021-04-20
日常の学び
日曜日に中学生の娘と一緒に家族シェアOKのセミナー動画を視聴しました。
10代に向けた著書である『極(エッセンシャル)アウトプット:「伝える力」で人生が決まる』の出版記念セミナー。
本自体はまだ途中までしか読んでいないようですが、セミナーは一緒に視聴できそうな時にと思い誘ってみたところ
「少ししか観ないかもしれないよ」と返答されましたので、
私は「3分でも5分でもいいし、飽きたらゲームしながらでもいいから出来るだけ聴いてね」と伝えセミナー動画を一緒に観ることになりました。
3分程でゲームを取り出し、ゲーム内に時間計測が出来る機能があるものでそこから5分のカウントダウンをスタートさせてました。
寝転んで動画視聴する私の横で座って動画視聴する娘。
その後に気づいたら15分程時間が経過してました。知っている内容の部分のためかウトウト、そして寝てしまったようです。
で、「寝てたしょ」と言われました(笑)
スッキリしたので座って一緒に動画視聴を開始。ちゃんとまだ観ていたのねと思うのでした。
そこからは、セミナーの内容に合わせて説明しながらマジメに観る部分、講師の話で娘のツボに入るポイントが所々にあったようで大爆笑している部分、一緒に声を出し楽しみながら内容を吸収する部分など工夫しながら観たため学びも多い充実した時間になりました。
後半の質疑応答のセッションは、また今度ということになりましたが、結局述べ90分のセミナー動画を楽しく視聴することが出来ました(^^)
情熱と冷静
2021-04-19
日常の学び
先週の金曜日はリーダー教育に関するセミナーに参加し、リーダーにとって大切な考え方や行動を学びました。
内容は伏せますが大きく分けると2つ、「ホット」と「クール」
「何が何でも成功させるぞ」というような情熱的な思い。そして、成功に導く冷静な判断や計画。簡単に言うとそんな感じです。
創業社長であればホットに寄りやすいですし、後継社長であればクールに寄りやすい気がします。
ホットだけだと息切れするし、クールだけだと信頼関係を築けないため、会社も個人も活動が続けられなくなります。
だからこそリーダーたるもの「何のためにやっているのか」と「どうしたいのか」を明確にすることで心を燃やし、そして「どうやるのか」と「やるための数字」を冷静に掲げ行動していくことが大事です。
最近はホットの要素が強くなっているので、少し冷静さを意識しないといけないかなって感じてます。